会社概要
会社名:株式会社マツシマメジャテック
創業:1946年1月
事業内容:産業用レベル計測機器・電動操作機器・コンベヤ周辺機器・制御機器・環境関連機器の設計・製作・販売
従業員数:111名(2025年2月時点)
多くの日本企業がデジタルトランスフォーメーション(DX)の必要性を認識し、基幹システムの刷新や業務プロセスの見直しに着手しています。ですが、その裏側では多くの試行錯誤や現場の苦労が付きものです。実際には、想定外のトラブル対応や細かな業務フローの再構築など、地道な作業がDXの成否を左右します。
今回は、YEデジタル Kyushu(YDK)が提供する「MONQX(モノクロス)」ブランドのシステム・サービスを導入して3年が経つ、株式会社マツシマメジャテックに取材しました。現場で導入から安定した運用に至るまで尽力された、杉山さん・西岡さん・安田さんの御三方と、それをサポートしたYDKの大石・大倉を交えて座談会形式で話を伺いました。
導入製品・サービス
- MONQX ERP(mcframe 7)
- MONQX Cloud MS
- MONQX Care
目次
旧システムのサポート終了と課題の表出を機に「MONQX」を導入
ーー本日は、マツシマメジャテックさんが取り組まれた「DX推進」の裏側を、導入支援を行ったYEデジタル Kyushuのメンバーとともにお伺いします。さっそくですが、まずはマツシマメジャテックさんの歴史や強みからお聞かせいただけますか?
弊社は1946年に創立し、戦後の産業復興期には炭鉱や鉄鋼、電力業界向けの計測機器などを提供してきました。培ってきた独自の計測技術を強みに、近年は河川の水位センサーや粉塵濃度の計測機器といった防災関連装置の製造など、新たな領域にも挑戦しています。
私の所属する生産部としては、「納期と品質」をどう守るかが使命ですが、裏側の生産管理も同じだけ重要なので、よりDXを進めていく必要性を感じていました。

ーーDX推進の経緯や背景についても、教えてください。
私は、長く社内の基幹システムの管理を担当してきました。以前は、自社開発システムと富士通のFlexBOMを組み合わせたものを導入していまして。導入当初は十分に機能していましたが、FlexBOMのサポート終了が迫り、不具合対応が難しくなるリスクが高まっていました。
それに加えて、業務が属人化していたことも課題でした。担当者が変わると、在庫や受発注管理のノウハウごと抜け落ちてしまううえに、エクセルや担当者の記憶に頼って管理しているケースも多かったので、次世代に知見をつなぐ仕組みを作らなければいけないと感じていたんです。

個々の担当者ベースで業務が回ってしまっていたので、システムを使って業務を標準化することは重要課題でしたよね。会社の土台を支える仕組みは、このタイミングでしっかり再構築したいと考えていました。

それから、会社の近くに河川があって、過去にはここ一帯が浸水したこともあるので、自然災害へのリスク対策としてもデータのクラウド化が必要でした。
ーーでは、旧システムのサポート終了やさまざまな課題解決のために新たなシステムの導入をお決めになったんですね。
はい。やはり、FlexBOMのサポート終了が一番大きかったですね。DX以前に日常業務に影響が出る恐れがありましたし、不具合が発生しても迅速に対応できませんから。それで、今こそシステムを刷新して管理体制を見直そう、という話になったんです。
システムのリプレイスは費用や時間、労力の面で大きなコストがかかりますが、会社として成長し続けるために不可欠な投資だと経営層も考えて決断に至りました。そんなときに、FlexBOMの提供元の富士通さんにYEデジタル Kyushuさんをご紹介いただいたんです。
ーー今回、YEデジタル Kyushuがマツシマメジャテックさんに提供したシステム・サービスは、どのようなものでしょうか?
弊社が提供する「MONQX」のシリーズのうち、「MONQX ERP」と「MONQX Cloud MS」「MONQX Care」を採用していただきました。「MONQX ERP」はERPを中心とした製造業向けの業務コンサルティングのサービスで、中でも生産管理や販売管理、原価管理などに対応した統合パッケージの「mcframe 7」を導入いただいています。
大きなカスタマイズをしなくても幅広い管理業務が完結するので、運用が安定しやすいのが特徴です。また、10年でサポートが切れることはなく、永続保守ができるので、安心して活用いただけます。「MONQX Cloud MS」はAWS(アマゾンウェブサービス)を使ったクラウド化のサービスで、「MONQX Care」は弊社が提供するシステム全般の運用・保守サービスです。

実際に「mcframe 7」は機能がたくさんあるので、カスタマイズはほとんどせずに標準仕様で導入しました。これを機に業務フローと管理体制を見直そうとしていたので、我々が「mcframe 7」の仕様に合わせていく考え方でしたね。
「がんばったら、良い景色に変わるけん」。社内を説得して運用を推進。原価管理の整備にも着手
ーー実際に「MONQX」シリーズの導入が決定してからは、どのようにプロジェクトを進めていったのでしょうか。
新システムの導入やクラウド環境への移行は軌道にのれば便利な半面、社内の体制構築や運用ルールの整備が追いつかないとスムーズに進まず、想定外のトラブルが起きがちです。そこで、マツシマメジャテックさんと密に連携しながら、要件定義からマスタデータの整備、テスト稼働、本稼働、社内教育までを段階を踏んでサポートさせていただきました。
結果的に無事に導入・運用できたのは、特に生産部と総務課をはじめとする皆様が協力して、業務標準化や適正な生産管理に向けて積極的に動いてくださったのが大きかったです。

ーープロジェクトを進めるなかで、大変だったことは何ですか?
私はプロジェクトのリーダーなのですが、やはり導入に対して社内の理解を得るのが大変でしたね。社員に「今のままでも業務は回ってるのに、なんで変えたね」と言われていました(笑)。そのたびに、「そう言わんでね、がんばったら良い景色に変わるけん」と言っていましたね。
ーーそこから、どのように理解を得ていったのでしょうか。
そこはもう、地道に説得して回っていました。導入は経営層の判断でもあったので、トップダウンで浸透していった面もあります。
他にも苦労したことはいろいろありますが、生産現場からすると、とにかく素材の在庫管理がポイントでした。以前はエクセルでだいたいの素材の管理をしていて、実はあまり正確な原価や粗利が把握できていない部分がありました。ですので、一から作らないといけないデータがあったことが大変でしたね。
それから、弊社には長納期の電子部品や一部を切断して使う素材など、正確な管理が難しいものが多いんです。例えば1mの素材があって、そのうち40cmを製造に使用した場合、残りは60cmになりますよね。こうした変動していく在庫の管理を「mcframe 7」でどこまで対応できるのか、正直不安がありました。
でも、YDKさんと相談しながら進めるうちに、運用ルールや管理体制の見直しとマスタ整備などで管理できることが多いとわかりましたね。

素材の中には高価なものもあったので、高い精度で管理できるようになって良かったです。
実は、本稼働になってから弊社側で素材の単位を間違えて入力してしまっていたことが発覚するトラブルがあって、その対応も大変でしたね…(笑)。困り果てていたら、大石さんがかけつけて一緒に対応してくださいました。
あのときは大変でしたよね(笑)。無事に解決して何よりです。

「mcframe 7」の導入で、価格交渉や見積もり発行がスムーズに
ーー紆余曲折を経て導入してからは、どんな変化を実感されましたか?
やはり、素材の原価と粗利の管理がしっかりとできるようになったことは大きいですね。クライアントに値上げの交渉をする際、原価の値上げを根拠に明確な説明ができるようになりましたから。
実際、あるクライアントに「mcframe 7」の管理データの一部を赤裸々に提示して交渉したら、他社さんは受け入れられていない中、弊社だけ値上げにご承諾いただけたんです! 価格改訂がスムーズに進むようになったのは、本当に大きな変化でした。
あと、これまで各担当者の頭の中やエクセルに散らばっていた在庫状況や素材の発注タイミングが、今はリアルタイムで確認できるようになったので、クライアントに対して納期や見積もりを正確かつスピーディーに出せるようになりました。属人化が解消して、一貫した体制をとれるようになって良かったです。
それから、何かあったときはYDKさんに相談すれば、早い段階で解決策を提示してもらえるようになったことも安心です。以前、トラブルが起きたときもすぐに対応いただけました。本当はサービスの対応範囲外だったと思いますが…。

システムをクラウド化したことで、災害や交通機関の乱れがあってもリモートワークで対応できるようになったのは大きいですね。加えて、ライセンス付与を一部の社員に絞ったことで担当者が明確になり、「この手続きは誰が承認するのか?」といった混乱が減ったのもメリットでした。
DXは目的設定と地道なデータ管理から。ITに詳しくなくても推進は可能
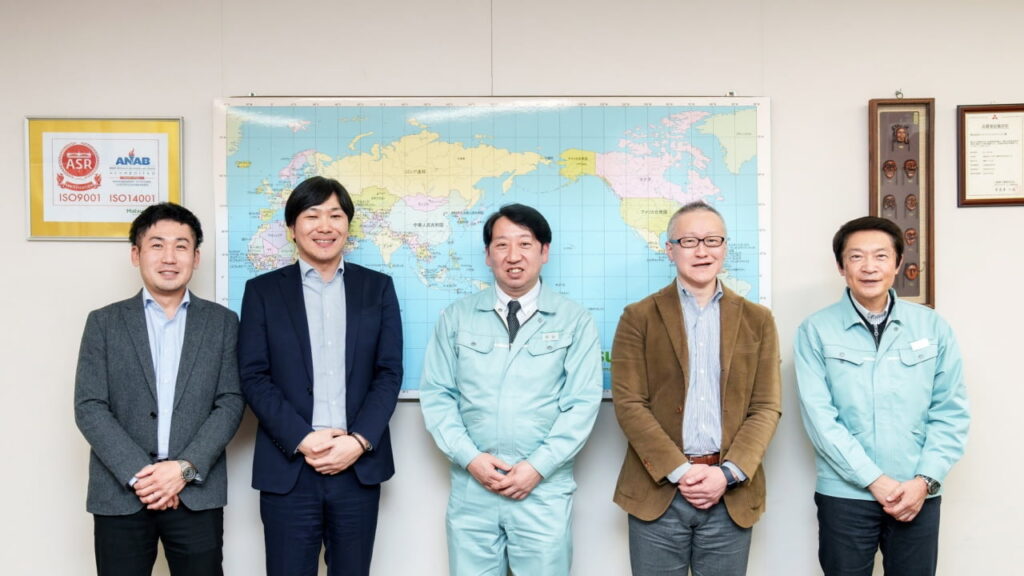
ーーDXを進めるうえでの今後の展開について、お聞かせください。
まだ課題はあるので解消していきながら、「MONQX」シリーズ活用のメリットを最大化させたいです。3年かけて溜まったデータをこれからどう活用していくかが直近のプロジェクトですね。原価と製品価格の連携をさらに進めて、価格交渉に活かしていきたいです。
また、今後はさらに細かい数字を出せるように精度をあげて管理していくことで、経営判断にも活かせるようにしていきたいですね。
あとは、データをサイネージに連携することで、各事業所で同じ情報を手早く閲覧できるようになりますし、海外のグループ会社やパートナー会社と情報を連携できるようにもなります。ご要望やご状況に応じて、そういったご支援もしていけたらと思います。
ーー最後に、今DXに向けて動こうとしている方や課題を感じている方に向けて、メッセージがあればお願いします。
システムの刷新を機にDXについてかなり勉強したのですが、やはりどこをどのようにDX化して、それでどんな効果を得られるのかをはっきりさせておくことが大事だと思いました。何を目指すのかをしっかり目標として設定しないと、目的に沿ったシステムやサービスを選ぶことも難しくなってしまいますし、費用対効果が得られないケースもあると思います。
おっしゃる通りですね。DXは夢のある言葉ですが、簡単には達成できない難しさもあります。まずは日々の業務に必要なデータをしっかり入力して管理するところから始まるんです。データを正値にするという守りの作業をしてはじめて、攻めの経営ができると思っています。
一方で、DXはITに詳しくない方でも推進することは可能です。むしろ、支援先に詳しくないお客様が多い状況が普通なくらいです。それよりも、新しい業務フローや管理体制を作っていこう、という意欲のほうが大事だと思っています。ITやDXに自信がない方こそ、ぜひご相談いただけたら幸いです。









